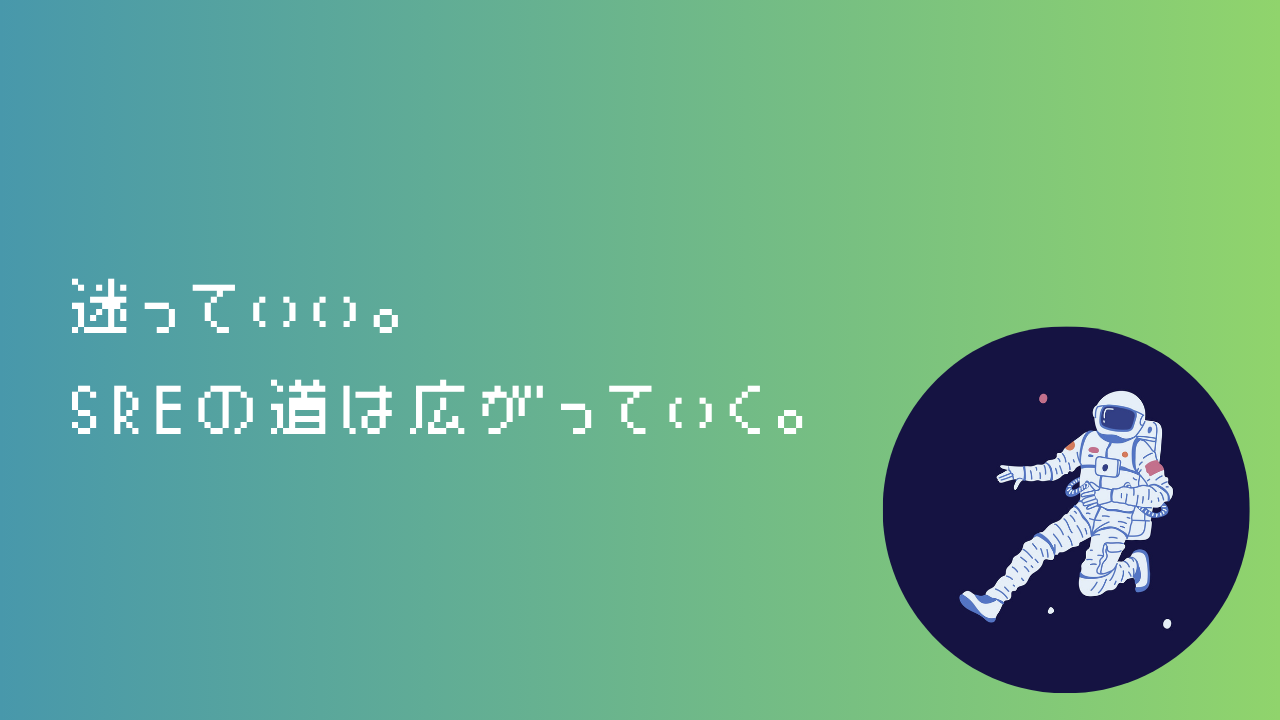私がSREキャリアに不安を抱いた理由

なぜ「SREの将来性」は見えづらいのか
「このままSREを続けていて、数年後の自分はどこに立っているんだろう」。そんな不安を最初に強く意識したのは、私自身がSREというロールに深く関わり始めた頃でした。インフラもコードも触るし、オンコールにも出る。
障害対応にもSLO設計にも関わる。やっていることは多いのに、「この先どんなキャリアにつながるのか」がはっきり見えない感覚が常につきまとっていました。
ソフトウェアエンジニアであれば「アーキテクトを目指す」「プロダクトのテックリードになる」といったイメージが比較的描きやすい。一方でSREは、開発と運用、プロダクトとプラットフォーム、ビジネスと技術のあいだに立つ仕事です。
だからこそ、担当する範囲も期待される役割も会社ごとにかなり違います。「うちのSREはほぼインフラ」「うちのSREはプラットフォームチームに近い」「うちのSREは文化づくりがメイン」といった話が普通に存在します。
この「会社によって役割がバラバラ」という状況が、SREの将来性を余計に見えづらくしていると感じます。同じSREという肩書きでも、何をやってきたか、どこに軸足を置いているかが大きく違う。
その結果、「転職市場で自分はどう評価されるのか」「このままここでSREを続けていいのか」という漠然とした不安が生まれます。私自身もまさにその渦中にいました。
そもそもSREは「定義が揺れる職種」である
Google公式の『Site Reliability Engineering』や『SRE Workbook』では、SREはソフトウェアエンジニアリングを用いてサービスの信頼性を高めるロールとして定義されています。
SLOやエラーバジェット、トイル削減、ポストモーテム文化といったプラクティスも明確に語られています。しかし現場に目を向けると、その定義がそのまま導入されているケースはむしろ少数派です。
実際には、「インフラチームをSREと呼び替えた」「監視や運用を任されていたチームにSREの看板が乗った」など、名前だけが先に独り歩きしている組織もあります。
すると、「自分は本当にSREをやっていると言えるのか」「ただの都合のいい何でも屋になっていないか」といったモヤモヤが、キャリアへの不安に直結していきます。
ここで大事なのは、「SREの定義が揺れているからこそ、不安になるのは自然なことだ」と一度認めてしまうことだと思っています。職種としてまだ歴史が浅く、各社が模索している最中のロールだからこそ、キャリアパスもきれいな図にはなりません。
むしろ、その揺らぎを前提にしながら、自分なりの軸をどう見つけるか。その問いからしか、SREとしてのキャリアは語れないのではないかと感じています。
SREのキャリアは「3つの系統」に分かれる

キャリアの不安を減らすには「系統で見る」のが有効
SREのキャリアが見えづらい最大の理由は、「SRE」という言葉にあらゆる役割が詰め込まれてしまっているからです。インフラ、プラットフォーム、品質、開発生産性、オンコール運用、自動化、SLO文化づくり・・・。
すべてを一人で背負うことはできませんし、人によって得意領域もまったく違います。
この“ごちゃまぜ状態”を解くには、「SREを3つの系統に分けて考える」とキャリアが一気に見えやすくなります。
これは海外でも日本でも一般的に語られる整理で、私自身が多くのSREのキャリア転換を見てきた中でも、非常にしっくりくる枠組みです。
① プラットフォーム系 SRE(Platform / Infrastructure SRE)
クラウド基盤、Kubernetes、CI/CD、ネットワーク、Observability基盤などサービスを支える土台を扱う系統です。
いわゆるインフラエンジニアやプラットフォームエンジニアの延長線上にあり、技術志向の強い人が多い領域です。
この系統は転職市場でもニーズが高く、技術のアップデート速度も速い分、専門性がリニアに評価されやすいという特徴があります。
② プロダクト系 SRE(Product Reliability / Application SRE)
アプリケーションの信頼性に直接関わるロールで、SLI/SLO設計、エラーバジェット運用、パフォーマンス改善、レジリエンス設計などを扱います。
アプリケーションの仕組みに理解が必要で、開発チームとの連携が非常に重要になります。
「技術 × コミュニケーション」の両輪が求められるため、ビジネスに近い視点を持ちたい人にもフィットします。
③ プロセス・文化系 SRE(Process / Culture SRE)
ポストモーテム文化、トイル削減プロセス、オンコール運用の仕組み化、DevOps文化の醸成、横断組織のファシリテーションなど、組織マネジメント寄りの側面が強いSREです。
この領域は意外にも転職市場で評価されやすく、特に「SREチームの立ち上げ経験」や「DevOps推進の経験」は希少で、事業会社からのニーズが増え続けています。
“どの系統を軸にするか”でキャリアの未来が変わる
この3つの系統はどれも重要ですが、キャリアの軸を意識せずに「何でも屋SRE」を続けてしまうと、数年後に評価されにくい状態に陥りやすいです。逆に、いずれかの系統で強い軸を作ると、市場価値は大きく上がります。
私自身も最初は曖昧なSREロールで悩んでいたのですが、「文化系」と「プロダクト系」の中間を得意領域として見定めたことで、キャリアの方向性が明確になりました。自分の得意と興味を軸に、どの系統で戦うかを見極めるのは、SREキャリアの最初の大きな分岐点だと感じています。
SREが市場で評価される理由

変化に強い組織をつくれるエンジニアだから
SREというロールが特に評価されるのは、「技術のスペシャリスト」だからではなく、「変化に強い組織をつくれる人」だからです。
クラウド移行、マイクロサービス化、リリース頻度の増加、AIの導入など、企業はこれまで以上に“変化し続けること”を求められています。
そのとき、インフラ・アプリ・運用・ビジネスのあいだをつなぎ、変化と安定のバランスをデザインできる人材は希少です。だからこそ、SREが市場で高く評価されるのは自然な流れだと言えます。
技術だけでなく、判断を担える人材が不足している
SREは「コードが書ける」だけでは務まりません。SLOを定義し、トレードオフを説明し、改善の優先度をつけ、障害時の判断に責任を持つ。技術と意思決定の両方を扱うという点で、他のロールとは一線を画します。
この判断の能力は代替しづらく、経験を積むほど市場価値が上がっていく領域でもあります。
クラウドネイティブ化・AI導入で、信頼性の重要度が急上昇している
Kubernetesやサーバーレス、分散システムが当たり前になった今、可用性やレイテンシの問題はより複雑になっています。さらにAI導入の加速により、「意味の正確性」「振る舞いの一貫性」「コスト最適化」など、従来SREでは扱わなかった新しい信頼性の層が増えています。
こうした複雑性の増加に対して、SREの考え方は極めて相性が良い。だからこそ、多くの企業が「SREを置きたい」「SREに相談したい」と考えるようになっています。
文化を変えられるエンジニアはどこでも必要とされる
信頼性は技術だけでは成立しません。
SREはポストモーテム文化、オンコール運用、SLOによる対話など、組織の“ルール”そのものを設計するロールでもあります。
技術を通して文化を動かせる人は、業界全体を見ても少数です。だからこそ、転職市場では常に高い評価を受けますし、事業会社でも「長期的に組織を強くできる人材」として重宝されます。
つまりSREの将来性は、スキルではなく「役割」に宿っている
特定技術の人気が下がれば職が減る・・・という種類の仕事ではありません。SREが担うのは、技術と文化のあいだをつなぐ役割。
その役割が必要とされる限り、SREという職の将来性がなくなることはありません。
むしろ、AI時代で信頼性の概念が広がっていくほど、SREの出番は増えていくはずです。だからこそ、今このキャリアを歩み始めるのは決して遅くありませんし、むしろ追い風の中にいると言えます。
SREキャリアの到達点はどこにあるのか

到達点①:SREスペシャリストとして“深める”道
SREとして専門性を深めていくと、より高度な技術領域を扱うポジションに進むことができます。
たとえば、分散システムの信頼性設計、オンコール運用モデルの刷新、SLO/SLIの体系化、自動化基盤の構築などです。
また、Google のように「シニアSRE → スタッフSRE → プリンシパルSRE」と専門職としてキャリアを積み上げるモデルも増えています。特にクラウドネイティブ化・AI導入が進む企業ほど、深い専門性を持つSREの需要が高まっています。
到達点②:プラットフォームエンジニアリングへの発展
SREの経験を積むと、次のキャリアとして「プラットフォームエンジニアリング」に進むケースも多いです。
開発者体験(DX)の向上、セルフサービス基盤の構築、IDP(Internal Developer Platform)の整備など、組織全体の開発の仕組みを作る仕事です。
共通しているのは、どちらも「仕組みで組織の生産性を上げる」という思想。SREからのキャリアパスとして、とても自然な選択肢です。
到達点③:エンジニアリングマネージャー・VPoEへの道
SREは技術だけでなく、判断・対話・文化づくりを日常的に扱います。そのため、マネジメント側へ進む人も多く、「エンジニアリングマネージャー」や「VPoE」にキャリアが接続しやすいのも特徴です。
特にSLOやポストモーテム文化の導入を通じて、「チームをどのように支えるか」「正しく変化させるか」を体験しているため、組織づくりに強いエンジニアとして評価されます。
到達点④:プロダクト側に移り、PMとして活躍する道
信頼性という視点でプロダクトを観測してきた経験は、実はPMと非常に相性が良いです。
SLOは「ユーザー体験をどう定義するか」という話ですし、エラーバジェットは「機能開発と品質のトレードオフをどう判断するか」という話でもあります。
そのため、SREからPMに転身する例も増えており、「技術に強いPM」として市場価値が高まる傾向があります。
到達点⑤:AI/SRE(AISRE)という新しい専門領域
近年注目されているのが、AI時代の信頼性を扱う「AISRE(AI Site Reliability Engineering)」です。
生成AIの品質劣化、ドリフト、検索精度低下、安全性など、従来のSREだけでは扱いきれない信頼性の層が登場しています。
今後、AIがあらゆるプロダクトに統合されていく中で、AISREの専門家は確実に必要とされるでしょう。ここはまさに、これから市場が広がる新領域です。
結論:SREはキャリアの終着点ではなく、広がり続けるフィールドである
インフラ、ソフトウェア、AI、組織文化、意思決定。その全部にまたがるのがSREというロールです。そのためキャリアは一方向ではなく、複数の専門領域へ枝分かれしていきます。
つまり、SREは「次のキャリアを狭める職」ではなく、「選択肢を増やす職」です。深く行く道も、広げる道も、ビジネス側へ行く道もある。将来性という観点では、非常に強いポジションにあります。
私が「SREというキャリア」に希望を感じている理由
理由①:技術と組織の両方を動かせるエンジニアは希少だから
SREを続けていると、「技術だけ強い人」「組織だけ動かせる人」と出会うことは多いですが、その両方を扱える人は本当に少ないと感じます。
信頼性はコードだけで作れず、文化だけでも作れません。その両方に触れられるSREは、どの現場でも重宝されますし、キャリアとしての希少価値があります。
理由②:どの企業も信頼性の専門家を求め始めている
可用性・レイテンシ・セキュリティ・自動化・オンコール・AIの品質。これらは、時代が進むほど複雑になり、簡単には扱えない領域です。
企業は「信頼性を専門に考えられるエンジニア」を必要としており、SREはその期待に最もフィットするロールです。
これは単なる流行りの職種ではなく、今後10年〜20年にわたって必要とされる長期的な需要だと感じています。
理由③:SREは“どこにいても通用する”普遍的なスキルが身につく
システムの観測、原因分析、改善サイクル、SLI/SLO、ポストモーテム、自動化、運用の最適化。これらは業界や技術スタックが変わっても通用するスキルセットです。
SRE経験を持つエンジニアは、どのプロダクト・どの企業でも即戦力になりやすいという強みがあります。
理由④:AI時代でさらに領域が広がるから
AIがプロダクトに組み込まれると、従来の「落ちた/遅い」という問題に加え、「意味がずれる」「モデルが静かに劣化する」「安全性が揺らぐ」というまったく新しいタイプの信頼性問題が生まれます。
AISREのような新領域は、SREの進化そのものです。
つまり、AIによってSREの仕事が減るどころか、SREの価値はむしろ強まると考えています。
理由⑤:SREは“キャリアの居心地”がいい
最後は個人的な理由ですが、私はSREの仕事が好きです。システムと人の両方に向き合えること、改善がチームに伝播していく瞬間を目撃できること、関係性が変わっていく実感を得られること。どれもエンジニアとしてのやりがいに直結しています。
「どう動けば、チームが前に進むのか?」という問いに向き合い続けられるのは、他職種では得がたい体験です。だからこそ、SREのキャリアに希望を感じています。
結論:SREは“未来に強いエンジニア”を育てるキャリアである
SREのキャリアパスは一方向ではありません。専門性を深める道も、組織を支える道も、AI領域に踏み出す道もある。どれも今後のエンジニアリングに必要とされる領域です。
SREは、キャリアを狭めるどころか、むしろ選択肢を最大に広げる職種だと私は思います。