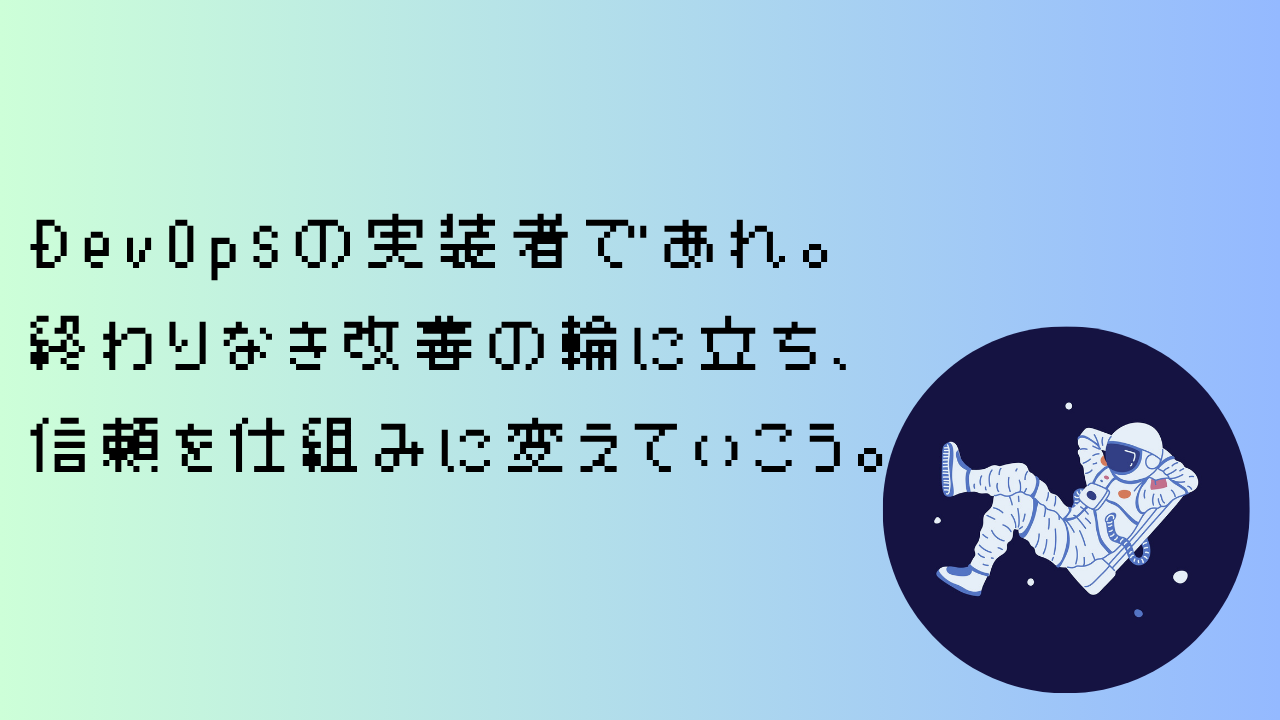なぜ、このサイトをつくろうと思ったのか
「SRE」と聞くと、どんなイメージを思い浮かべますか。GoogleのSRE本に出てくる理想の運用文化?自動化されたCI/CDパイプライン?あるいは、システムを止めない最強のインフラチーム?
正直に言えば、私自身も最初はそのどれかでした。けれど、SREという言葉を追いかければ追いかけるほど、そこにあるのは技術よりも人間の営みだと気づいたのです。
信頼性とは、コードやツールだけで完結するものではありません。「誰かが何かを信じて任せられる状態」。それをチームや組織の中にどう設計するか。そこにこそ、SREという仕事の難しさと面白さがあると感じています。
だからこそ、このサイトをつくりました。SREとDevOpsの思想を、現場の観測記録として残すために。うまくいった話よりも、うまくいかなかった経験を丁寧に言語化するために。
SREエンジニアラボは、専門家が答えを教える場所ではなく、“現場で考え続ける人たちの小さな実験室”です。
SRE組織を立ち上げたときの話
「信頼性を数値でコントロールできる」と思っていた頃
数年前、私はある会社でSRE組織の立ち上げを任されました。インフラとアプリのあいだに横串を通し、信頼性を高める取り組みを全社的に推進する――そんな使命を胸に、資料を作り、経営層に提案し、小さな横断チームを発足させました。
当時の私は、信頼性=安定稼働、可用性、レスポンスタイム、つまり「数値で見える指標」だと信じていました。メトリクスを整え、ダッシュボードを用意すれば、組織全体の意識も変わるだろうと。信頼性とは“定量的にコントロールできるもの”だと、どこかで思い込んでいたのです。
理想と現実のあいだで、SREチームが“板挟み”になる
しかし、現実はそう甘くありませんでした。障害対応は日常茶飯事で、Slackには常に緊急対応スレッドが立ち、アラートの音が夜中まで鳴り続ける。可視化したデータはチームごとに見方が異なり、「どの数字を信じればいいのか」が議論になる。開発側は「新機能を止めたくない」、運用側は「安定を最優先したい」。どちらの意見も間違っていないのに、議論は平行線をたどりました。
SREチームはその“間”に立つ存在であるはずなのに、いつしか“板挟み”の象徴になっていました。どちらの立場にも寄り添いきれず、「SREチームがまた口を出してきた」と言われることもありました。ある開発リーダーは「信頼性って、つまり誰のための数字なの?」と問いかけてきました。その一言が、胸に刺さりました。
正しさよりも、現場の信頼を取り戻すために
確かに、私たちは「信頼性を高めよう」という正義のもとに動いていましたが、気づけばその正義が、他のチームの“現場の正義”を押しつぶしていたのかもしれません。開発チームにとっては、信頼性よりも“スピード”が信頼そのものだったのです。リリースを止めないこと、顧客の要望に応えること――それもまた、別の形の信頼でした。
SREという言葉は、たしかに未来志向で、かっこよく聞こえます。しかし、実際の現場では「文化を変える」と言うほど簡単な話ではなく、ひとつの提案が誰かのタスクを増やし、調整の数だけ摩擦が生まれます。信頼性を高めるための会議が、信頼関係をすり減らすことさえありました。
あの頃の私は、正しさと信頼のあいだで迷いながらも、毎週の障害対応に顔を出し、各チームのMTGに参加し、細かなSlackスレッドを追いかけ続けていました。今思えば、それは“信頼性の実装”というより、“信頼そのものを取り戻すための観測”だったのかもしれません。
なぜ失敗したのかを“観測”してみた
技術ではなく、文化の壁にぶつかった
あの一年を振り返ると、技術的なミスよりも、文化的な断絶のほうが大きな壁でした。
私がいくら資料を整え、スライドで「SREの役割」を説明しても、どこか他人事のように受け止められる空気がありました。「SREが何をする人たちなのか」「なぜこの取り組みが必要なのか」――その共通認識を、私は十分に作れなかったのです。
SREという言葉は理解されても、“SREの意味”は伝わっていなかったのだと思います。
「文化を変える」と言うのは簡単ですが、それは誰かの仕事を変えるということ。つまり、誰かの慣れや誇りを揺らす行為でもあるのです。
“信頼性”の定義が、チームごとに違っていた
あるとき、障害レポートを配信したあとに、開発チームのリーダーからメッセージが届きました。
「言ってることは正しい。でも、俺たちは今日もデプロイを止められないんだよ。」
その言葉が胸に刺さりました。彼らは軽視しているのではなく、目の前のユーザーとプロダクトを守るために戦っていたのです。彼らにとっての“信頼”とは、「動くものを止めないこと」でした。
一方で、私が掲げていた“信頼性”は、「障害を減らし、安定性を高めること」でした。どちらも正しい。けれど、視点の軸がわずかにずれていたのです。
その小さなズレが、やがて大きな溝になっていきました。
データよりも先に、“関係”を観測すべきだった
会議では理想がぶつかり、Slackでは議論がすれ違い、チーム間の温度差が日に日に広がっていく。
気づけば私は、“信頼性”という名の理想を掲げながら、誰かの信頼を失っていたのかもしれません。
観測・分析・改善。この三つを回す前に、「人と人との信頼をどう築くか」という一番大事な部分を、私は置き去りにしていました。
データよりも先に、まず“関係”を整えるべきだった――それが、私にとって最初の失敗の観測結果でした。
そこから見えてきた「信頼性」の本当の意味
“変化と安定”のあいだにある、人の判断
SREの本質は、変化と安定のバランスをデザインすることです。けれど、そのバランスは「技術」だけでは取れません。そこには、人の判断と、チームの合意という、数値では測れない要素が常に関わっています。
どんなに自動化が進んでも、どんなに監視が賢くなっても、最後に“決める”のは人間です。そしてその判断を支えるのが、「この人たちが言うなら大丈夫」と思える、人への信頼です。
失敗を責めない“観測文化”の始まり
私はあの失敗のあと、ポストモーテム文化を導入しました。障害を「誰の責任か」ではなく、「何が起き、なぜそうなったのか」を観測する機会に変える仕組みです。最初は、誰も積極的に書こうとしませんでした。失敗を共有することは、恥をさらすような感覚があったのだと思います。
だから、まずは自分から始めました。自分のやらかしを丁寧に記録し、経緯や判断の迷いまで書き残しました。
それを読んだ数人が、Slackのスレッドで「わかります」「自分も似たケースありました」とコメントをくれました。たったそれだけの反応でも、チームの空気が少しだけ変わった気がしました。
“失敗”が共有されたとき、信頼が生まれる
やがて、別のエンジニアが自分の障害対応を共有してくれました。原因は小さな設定ミス。しかしその投稿に、予想外の反響がありました。誰も責めず、みんなで「どうすれば再発を防げるか」を自然に語り合ったのです。そこで、ある若手がこう言いました。
「自分のやらかしを、文化の一部にできるっていいですね。」
その言葉を聞いた瞬間、胸の奥が静かに熱くなりました。
“信頼性”という言葉が、ようやく数字の外に出た気がしたのです。
稼働率やSLOではなく、人と人の関係の中で生きている――それが、私の中での「信頼性」の再定義でした。
あの日から、私は「仕組みを作る」よりも、「仕組みが育つ環境を整える」ことを意識するようになりました。
信頼は作り込むものではなく、共有された失敗の上に静かに積み重なるものなのだと。
SREエンジニアラボという実験室へ
この経験を通じて強く感じたのは、「SREの知識は、本だけでは学べない」ということです。
どんな優れた書籍やドキュメントも、現場での衝突・葛藤・工夫には敵いません。実際の組織で何が起き、どんな議論があって、どんな痛みを経て文化が生まれたのか。そこにしか、“実装された信頼”は存在しない。
だからこのサイトでは、SREやDevOpsの理論を語るよりも、現場の観測ログを記録することを大切にします。
成功も失敗も、過程も曖昧さもすべて含めて。「なぜこうなったのか」を、分析ではなく“観察”として書き残す。
このラボは、誰かの実験記録が、次の誰かの改善のきっかけになる場所でありたいと思っています。
このラボで目指すこと
SREエンジニアラボが目指すのは、“技術の正しさ”ではなく、“文化の成熟”です。
DevOpsの本質は、ツールでも自動化でもなく、「対話と信頼による連携の文化」です。私たちはその文化を、現場の中から観測し、言葉にしていきます。
これから書く記事は、
- SRE導入初期の失敗談
- 信頼性指標(SLO・エラーバジェット)の運用実例
- インシデント後のポストモーテム
- チーム文化を育てるためのコミュニケーション施策
など、現場で生まれたリアルな知見をもとに構成していく予定です。
このサイトの読者は、“答えを探す人”ではなく、“問いを共有する人”であってほしい。完璧を求めず、観測し、学び、仕組みに還元する。そのサイクルの中に、信頼性文化の芽が育つと信じています。
最後に
SREの仕事は、地味で、泥臭く、そして尊い。その本質は「トラブルを防ぐ」ことではなく、トラブルから信頼を取り戻す仕組みを作ることです。
私はこのラボを通じて、自分自身の失敗を“観測の素材”として残したいと思っています。うまくいかなかったことを記録するのは勇気がいりますが、それを共有することこそ、次の信頼を生むはずです。
終わりなき改善の輪に、立ち続けよ。
この言葉を、SREエンジニアラボの理念として掲げたいと思います。この場所が、あなたのチームの観測と改善のきっかけになりますように。