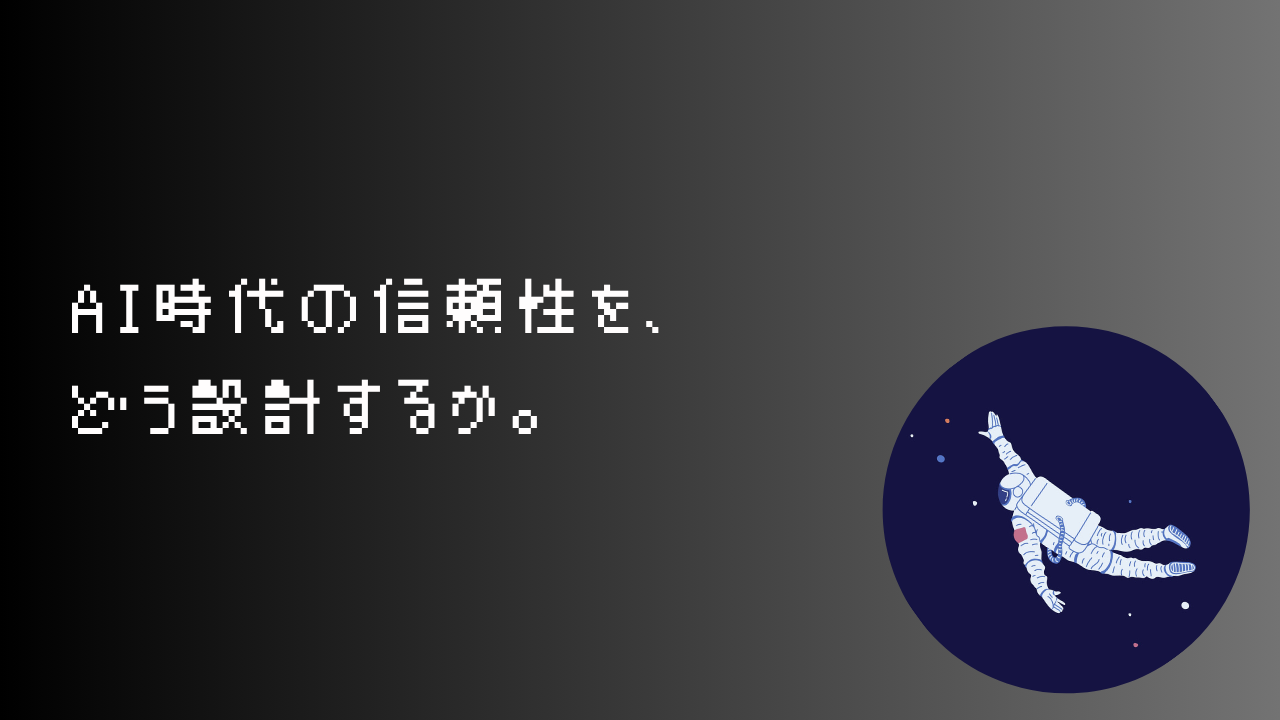AI時代に、なぜ「SREの未来」を問うのか
いま、AIプロダクトの現場では「すべてのダッシュボードがグリーンなのに品質が落ちている」という現象が静かに増えています。レイテンシもエラー率も異常なし。可用性も高いまま。けれど、ユーザーは「なんか違う」と感じ始める。理由は簡単で、AIには“意味が崩れる”という新しいタイプの信頼性問題があるからです。
ここで提唱されているのが AISRE(AI Site Reliability Engineering) という概念です。従来のSREが扱ってきた「落ちる・遅い・エラーを返す」から一歩進み、AI特有の「静かな劣化」や「意味のゆがみ」まで観測しようという試みです。
ただし、ここでひとつ疑問があります。AISREは本当に「SREの未来」なのでしょうか。それとも、AIという新領域を扱うための派生概念に過ぎないのでしょうか。本記事では、SREの思想(なぜ“信頼性”を研究するのか — SREエンジニアラボのはじまり)を軸に、AISREを思想として読み解きます。
AISREとは何か — “信頼性の対象”が広がりつつある
AISREは、従来のSREが扱ってきた信頼性の概念を「AI特有の失敗モード」にまで拡張した考え方です。ここで言う“失敗”とは、サーバーが落ちることでも、エラーを返すことでもありません。AIプロダクトにおける失敗は、もっと静かで、もっと見えにくい領域に潜んでいます。
たとえば、レイテンシもエラー率もすべて基準値内。それなのに、ユーザーの「再生成」が増え続ける。検索インデックスの鮮度が落ち、回答の根拠が数%ずれていく。あるいは、プロンプトをわずかに変えただけで、コストが40%跳ね上がる。こうした “意味的品質” の劣化は、従来のSREメトリクスでは捉えきれません。
AISREは、このギャップを埋めるために登場しました。AIモデル、埋め込み、RAG(Retrieval)、エージェント、そしてユーザー体験。これらをレイヤーごとに分解し、それぞれにSLI/SLOを設け、ロールバック単位を定義する。つまり、AIプロダクト全体を「観測可能な構造」として扱う試みです。
AIプロダクトは、本質的に揺らぐ存在です。同じ入力でも、昨日とは違う振る舞いをする可能性があります。AISREは、その揺らぎに対して「どこを見ればよいのか」「どこで止めるのか」「どこまで戻すのか」というガイドラインを与えようとしています。
従来のSREが扱ってきた信頼性の中心が「落ちない・遅れない」であるなら、AISREが扱う信頼性は「誤らない・逸脱しない・暴走しない」と言えます。対象範囲は広がり、観測すべきものは深く、そしてより曖昧で、人間の判断に寄り添う必要が出てきます。
AISREが生まれた理由 — “静かな劣化”をどう観測するか
AIシステムの難しさは、「壊れ方が静か」であることです。サーバーダウンのように一目で分かる障害ではなく、気づかないうちに“質”が落ちていく。ユーザーはなんとなく使いにくさを感じるものの、明確にエラーが出るわけでもない。こうした静かな劣化は、従来のSREメトリクスではほぼ検知できません。
たとえば、ユーザーに返す回答の「根拠の鮮度」が1〜3%落ちたとしても、CPU使用率も、レスポンスタイムも、エラー率も正常のままです。検索インデックスが古くなり、モデルの挙動がわずかに変化し、埋め込みモデルのバージョンがひっそりとアップデートされる。これらはログやメトリクスの表面には現れませんが、プロダクトの体験を確実に悪化させます。
ユーザーの「Regenerate(再生成)」が増え始めるのも、その典型的なサインです。再生成率はインフラのエラー率と連動しません。むしろ、システムが正常に稼働しているときほど、気づかないうちに悪化が進むことさえあります。つまり、AIの信頼性は“意味のレイヤ”で壊れ始めるのです。
AISREは、こうした曖昧で質的な変化を観測可能な指標として扱うためのアプローチです。意味的正確性(semantic accuracy)、根拠ある回答率(grounded answer rate)、検索精度(context precision)、意図推定の安定性、そしてユーザーの行動データ。これらをSLI/SLOとして定義し、健全性を継続的にトラッキングします。
重要なのは、AIの振る舞いが人間の認知モデルに影響を与えるという点です。AIのわずかなズレは、判断のズレにつながり、結果としてビジネスや意思決定を誤らせる可能性があります。だからこそ、従来の可用性中心のSREだけでは不十分なのです。
AISREの誕生は、「AIが社会のインフラになるなら、その振る舞い自体を観測しなければならない」という必然の流れだと言えるでしょう。
AISREはSREの拡張なのか、それとも別物なのか
AISREは、従来のSREを完全に置き換えるものではありません。むしろ、AIという新しい失敗モードに対応するために、SREの思想を拡張したものと捉えるのが最も正確です。つまり、SREの核心である「信頼性をエンジニアリングで管理する」という考え方はそのままに、扱う対象と観測すべきレイヤが大きく広がった形です。
従来のSREが見てきたのは、主にインフラとアプリケーションの健全性でした。可用性、レイテンシ、エラー率、スループットといった指標は、システムが“動くかどうか”を測るためのものです。一方、AIシステムでは動いていても壊れていることが普通に起こります。根拠がずれる、検索が弱る、モデルが静かにドリフトする、エージェントがループする――これらは従来のSREのダッシュボードを完全にすり抜けてしまいます。
だからこそAISREは、信頼性を「技術」だけでなく「振る舞いと意味」のレイヤでも扱おうとする試みなのです。たとえば、以下のような観点が追加されます。
- モデルの意味的正しさ(semantic accuracy)
- 検索の精度と鮮度(context precision)
- エージェントの意図推定の安定性
- 「再生成」の増加など、UXレイヤで起きる静かな劣化
- モデル/プロンプト/埋め込み/リトリーバの差分管理
こうした新しい監視対象はSREにとっては未知の領域ですが、根底にあるのは従来と同じです。つまり、「信頼性とは、技術と人の関係性で決まる」という原則です。SREが長年扱ってきたインシデント管理、ロールバック設計、カナリアデプロイ、SLOベースの議論。こうした実践はそのままAIにも適用できます。ただし、その“対象”が変わるというだけです。
言い換えれば、AISREはSREの終わりではなく、SREの進化形です。AIがプロダクトの中心になる未来では、SREが扱う信頼性の定義そのものが広がっていく。AISREは、その未来像のひとつと言えるでしょう。
レイヤードSRE:AI時代の「どこを見るか」問題
AIシステムの難しさは、「どこが壊れているのか」が従来より圧倒的に判別しにくい点にあります。CPUもメモリも正常、エラー率もゼロ、レイテンシも安定している。それなのにユーザー体験だけがじわじわ悪化していく――AIプロダクトでは、こうした静かな事故が頻発します。
AISREではこの問題に対処するために、AIシステムを複数のレイヤに分けて監視するアプローチを採用します。これはSREの「オブザーバビリティを構造化する」という思想を、AIに最適化したものとも言えます。
1. 基盤モデルレイヤ(LLMそのもの)
生成モデルや埋め込みモデルの品質・速度・安定性を観測するレイヤです。特に重要なのは、ttft(first token latency)やgoodput(役に立つトークン量/秒)といった、AI特有の指標です。モデルの微細な更新であっても挙動が変わるため、バージョン管理とロールバック戦略が不可欠です。
2. RAGレイヤ(検索と文脈生成)
検索結果の精度低下やインデックスの鮮度落ちなど、RAGの問題はLLMの品質以上にユーザー体験を左右します。context_precision@k や ingestion lag といったメトリクスを用いて、検索レイヤの“意味的健全性”を監視する必要があります。
3. エージェント/ツールレイヤ
プランナー、ツールチェーン、ルーティングなど、AIが考える部分の監視です。ここでは、ループ検知(loop_abort_rate)や安全ガード(unsafe_action_block_rate)が重要になります。正しく動いているのに無限ループしているといった、従来のSREでは想定しない失敗モードにも対応します。
4. プロダクト/UXレイヤ
ユーザーが違和感を感じるレイヤです。再生成率(regeneration_rate)や早期中断率(early_abort_rate)など、UX中心の指標が必要になります。ここが静かに悪化しても、インフラのダッシュボードはずっとグリーンのままです。
5. 横断レイヤ(ドリフト/コスト/安全性)
AIシステムは常に変化し続けるため、モデルのドリフト(semantic_accuracy_delta)、コスト暴走(token_waste_ratio)、安全ポリシー準拠など、横断的な観測が求められます。特に“サイレント更新”への備えとして、ロールバックスクリプトと差分評価(differential eval)は必須です。
このレイヤードアプローチは、AI時代のSREにとって「どこを見るべきか」を体系化するための非常に強力なフレームです。SREがAIに取り組む際、まずこの視点を持てるかどうかで、信頼性の議論の質が大きく変わります。
AISREの最初の一歩:現実的なスターターセット
AISREという概念は大きく見えますが、実務でいきなり全レイヤを完璧に扱う必要はありません。むしろ重要なのは、「最低限どこから始めれば破綻しないか」という現実的な視点です。これはGoogle SREが強調する“スタートスモール”の思想とも一致します。
ここでは、AIプロダクトを扱うチームがまず押さえるべき、現実的なスターターセットを整理します。
1. 意味(Semantic)系のSLI
AI特有の信頼性劣化は、表面的には見えません。だからこそ、最初に導入すべきは意味的な正確性の観測です。代表的なのは hallucination_rate(致命的誤答率)です。人手レビューやサンプリングでの計測でも構いません。重要なのは「意味的な品質を測る基準」を最初に置くことです。
2. 検索(Retrieval)系のSLI
RAG構成のプロダクトであれば、context_precision@k や ingestion lag は最初に押さえるべき指標です。特にインデックスの鮮度は静かに悪化し、ユーザー体験を大きく損ないます。検索基盤はAIプロダクトの“血流”であり、その健全性は本番品質に直結します。
3. 安全性(Safety)とUXの観測
unsafe_output_rate や false_refusal_rate のような安全系の指標、再生成率や早期離脱といったUX系の指標は、初期のAIサービスでも導入効果の大きいメトリクスです。少しの可視化でも、ユーザー行動の変化が驚くほど明確に見えてきます。
4. 経済性(Economics)の観測
AIはコストが指数関数的に吹き上がります。cost_per_successful_task や token_waste_ratio は、本番を維持するために必須のSLIです。多くの組織が隠れたボトルネックとして直面するのが、この経済性の劣化です。
5. ロールバック戦略(モデル・プロンプト・インデックス)
従来のSREではバイナリや設定を戻せば対応できましたが、AIでは扱う対象が増えます。モデル、埋め込み、インデックス、プロンプト、リランカー、プランナー――これらをすべて「デプロイ対象」として扱い、巻き戻す手段を準備する必要があります。最低限、スナップショットと固定化(pin)を行う仕組みが必要です。
AIプロダクトを支えるSREは、従来のインフラ観測だけでは不十分です。しかし、このスターターセットさえ揃っていれば、少なくとも「静かな事故」を見逃す確率は大きく下がります。
AISREは巨大な概念ですが、はじめの一歩は小さくても十分です。重要なのは、その一歩に“観測の視点”があるかどうかです。
AIの時代にSREが担うべき役割とは?
AIがサービスの中心に組み込まれつつある今、SREの役割は「インフラの安定運用」から「プロダクトとしての信頼性を守る技術文化の設計」へと拡張されています。これはSRE本来の思想と矛盾しません。
むしろ、Google SREが初期から語ってきた「信頼性はエンジニアリングで設計できる」という原点に戻る動きです。
AISREが提唱する新しいフレームは、AIの時代におけるSREの姿を次のように浮かび上がらせます。
1. 「意味の健全性」を守る守護者として
可用性やレイテンシのような従来指標に加えて、「意味の正しさ(semantic correctness)」をユーザーに届ける役割を持ちます。これはAIサービスにおける新しい“品質保証”であり、SREが扱う範囲はアプリケーションの内部ロジックにまで踏み込みます。
2. 変化し続けるシステムのエンベロープ管理
AIモデルは静的な存在ではなく、常に変化し続ける揮発的なコンポーネントです。モデル更新、インデックス再構築、プロンプト差し替え——AIシステムでは常にどこかが変わっています。この「絶え間ない変化」を前提に、どこまでが許容範囲か(エンベロープ)を定義することがSREの新しい役割になります。
3. レイヤ間の相互作用を理解するシステム思考者として
AIプロダクトはレイヤ単体では語れません。モデルの微細変更が検索精度を変え、検索精度がUXを変え、UXがフィードバックデータに影響する。その相互作用を理解し、全体のバランスを保つことは、従来型SREの「システム思考」と地続きです。
4. 文化をつくるファシリテーターとしてのSRE
0章でも述べた通り、「信頼性は関係性である」という思想はAI時代にもそのまま当てはまります。AIプロダクトでは、モデルの更新やインデックスの再構築など、境界線の曖昧な領域が増えます。だからこそ、失敗を共有し、観測を文化に変えるファシリテーションの重要度が増しています。
5. “静かな事故”を見逃さない観測者として
AIサービスは壊れ方が静かです。ログにもエラーにも現れず、ユーザーの違和感としてだけ積み上がっていく。この静かな事故を見逃さないために、意味、検索、経済性、安全性――複数の観測点を持つことが、SREに求められる新しい責務です。
AISREは単なるAI運用の新概念ではなく、SREの未来像そのものに近いものです。変化し続けるシステムで、どう信頼性を維持するか。その問いに対する最初の体系的な回答だと言えるでしょう。
AIを含む複雑なプロダクトの中心で、信頼性を設計し、観測し、改善し続ける存在。それがこれからのSREです。
まとめ
AISREという概念は、新しいようでいて、SREの思想に深く根ざしています。GoogleのSRE本が強調してきた「観測」「学習」「改善」「文化」。これらはAI時代でもまったく変わりません。むしろ、AIという“変化し続ける存在”を扱う今こそ、その重要性は増しています。
AIは落ちないかもしれない。けれど、意味を間違うことがある。検索が少しずつ劣化することがある。コストが静かに暴走することがある。UIがユーザーを迷わせることがある。こうした従来とは異なる失敗モードに対処するには、単なる監視や自動化では足りません。
必要なのは、「何が信頼性を形づくっているのか」を丁寧に観測し続ける姿勢です。技術だけでなく、ユーザー体験、チームの判断、文化の成熟。これらすべてが信頼性に寄与するという視点です。
SREエンジニア∞ラボの立場として
本サイトでは、AISREを単なるバズワードとして扱うのではなく、SREの思想と地続きのものとして捉え、実践者の視点から分解していきます。SREの本質は「信頼性を文化として育てること」であり、AISREの本質は「AI特有の変化を、その文化の中で扱う方法」を示したものです。
最初の「信頼性は関係性である」というメッセージは、AI時代にも変わりません。モデルの挙動を理解し、検索の鮮度を保ち、UXの違和感を拾い、チームに共有し、再発防止策を文化として育てていく。そこにエンジニアリングと人間的な対話の両方が必要です。
あなたの観測が、未来の文化を形づくる
AI時代のSREは、未知の領域も多く、正解もまだ定まっていません。しかし、どんな組織でも最初の一歩は同じです。「観測し、言語化し、共有する」。その小さな蓄積が、文化を育て、信頼性を支える大きな柱になります。
あなたが見た現象、気づいた違和感、解決できた問題――その一つひとつが、次の誰かの助けになります。SREは実装で未来を守る仕事です。そしてAISREは、その未来の形をともに描くための新しい視点です。
このラボでは、そうした一つ一つの観測をていねいに記録し、分かち合い、言葉にしていきます。AI時代の信頼性を、あなたとともに探求していくために。